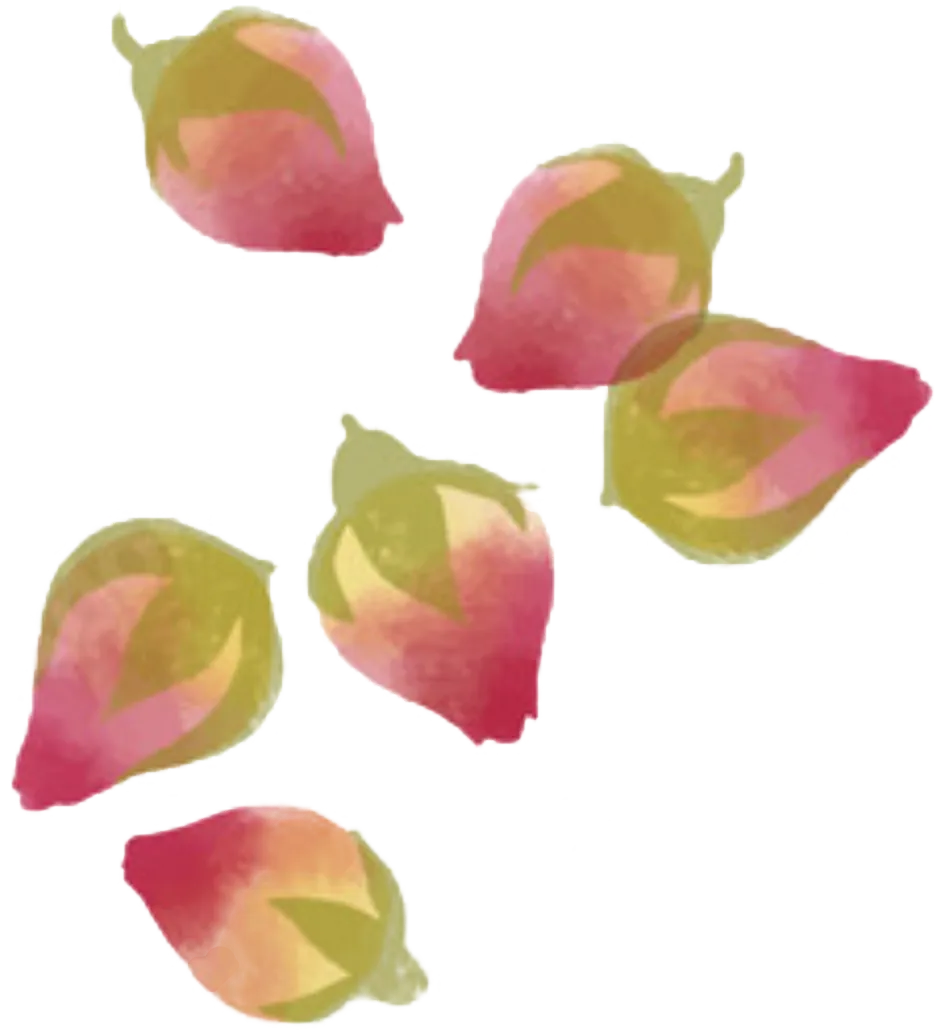加美漢方薬局が選ぶ、口内炎におすすめの漢方薬5選

口内炎を治すにはビタミンB群が有効です。しかし、繰り返す口内炎や、口内炎になりやすい体質の改善には漢方薬が向いています。体の熱を取る漢方薬(抗炎症作用のある漢方薬)で対処する場合が多いです。
この記事の目次
炎症がひどい
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
構成生薬:黄連(おうれん)・黄芩(おうごん)・半夏(はんげ)・乾姜(かんきょう)・人参(にんじん)・甘草(かんぞう)・大棗(たいそう)
消化不良・吐き気・下痢・みぞおちのつかえなどを改善する漢方薬で、体の熱(炎症)をとる効果もあります。黄連は抗炎症作用と健胃作用があり、特に胃内の過剰な熱を冷ますことで消化器系の炎症や不快感を抑えます。黄芩は黄連と同様に清熱作用(体の熱を取る作用)があり、特に上腹部の熱や炎症を鎮めるとともに、抗菌作用や鎮静作用もある生薬です。半夏は吐き気や嘔吐を抑える鎮吐作用に優れ、さらに胃内の水分代謝を整えて水滞を改善し、胃腸の気の巡りを良くします。乾姜は体を温める作用があり、胃腸の冷えを改善して消化機能を活発にし、半夏と組み合わせることで冷えと水の停滞による不調を取り除く生薬です。人参は胃腸の力を補って消化吸収を助け、全身の元気を養う補気薬として、消耗した体力の回復にも寄与します。甘草は調和作用があり、各生薬の働きを整えるとともに、胃粘膜を保護し鎮痙・緩和作用を通じて胃腸の過敏な動きを抑える生薬です。大棗は人参と同様に補気作用を持ち、さらに精神を安定させる効果もあるため、胃腸の不調に伴う不安やストレスの軽減もします。
黄連解毒湯
構成生薬:黄連(おうれん)・黄芩(おうごん)・黄柏(おうばく)・山梔子(さんしし)
体内にこもった強い熱・炎症・イライラ・不眠・のぼせ・口内炎・皮膚の赤みや腫れなどの症状を鎮める漢方薬です。黄連は強い苦味と清熱作用を持ち、特に心と胃の熱を冷まし、精神的な高ぶり・胃部の不快感・口内炎などを鎮めます。黄芩は肺や胆の熱を冷まし、抗炎症・抗菌作用に優れ、黄連とともに上半身の炎症を抑えることで、のぼせ・熱感・口の渇きなどを和らげます。黄連と黄芩は清熱作用を高める組み合わせです。黄柏は主に下焦、つまり下腹部や泌尿器系の熱を冷ます作用があり、利尿や抗炎症の働きも兼ね備えているため、身体の下部に生じる熱による不快感を改善します。山梔子は全身の熱を冷ます清熱瀉火薬で、特に心や肝の熱を抑えて精神を落ち着ける働きがあり、イライラや不眠、頭痛などを改善する生薬です。
茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)
構成生薬:茵陳蒿(いんちんこう)・山梔子(さんしし)・大黄(だいおう)
黄疸など肝胆系の熱に使う漢方薬で、特に皮膚や目の黄ばみ・口の渇き・便秘、尿の色が濃いなどに効果的です。主薬である茵陳蒿は胆汁の分泌を促進し、肝臓の機能を整えることで黄疸の原因となる熱を排出し、皮膚や目の黄ばみを改善します。山梔子は清熱作用に優れ、特に肝と胆の熱を冷ますことで、茵陳蒿の作用を補強しつつ、炎症や口渇、不眠、イライラといった熱証による随伴症状を緩和します。利尿作用も持つ生薬です。大黄は緩下作用を持ち、腸に滞った熱や老廃物を排出することで体内の熱を外に出し、特に便秘を改善して解毒を助けます。
温清飲(うんせいいん)
構成生薬:当帰(とうき)・黄連(おうれん)・地黄(じおう)・黄芩(おうごん)・芍薬(しゃくやく)・黄柏(おうばく)・川芎(せんきゅう)・山梔子(さんしし)
温清飲は、血の不足と熱の亢進が同時に存在する「血虚火旺(けっきょかおう)」の状態に用いられる漢方薬です。肌荒れ・のぼせ・月経不順・不眠・イライラ・便秘などを改善するのに使われます。黄連解毒湯と、血を補う基本の漢方薬、四物湯(しもつとう)を組み合わせた漢方薬です。当帰は血を補い血行を促進する代表的な補血薬で、肌や粘膜の潤いを保ちつつ、ホルモンバランスの乱れによる不調を整えます。黄連は清熱作用が強く、特に心や胃にこもる余分な熱を冷ますことで、不眠・口内炎・イライラなどの熱症状を改善します。地黄は血と陰を補って体に潤いを与え、熱によって消耗された体力を回復させ、熱を抑える陰液の基盤を整える生薬です。黄芩は抗炎症作用と清熱作用に優れ、特に上半身の熱を冷ましながら、肌の炎症や赤みを抑えます。芍薬は血を養うと同時に筋肉のけいれんや緊張を緩和し、月経痛や腹部の不快感の緩和にも役立つ生薬です。黄柏は下焦の熱を冷ます作用があり、泌尿器系や生殖器に生じる熱を鎮めて下半身の炎症症状を改善します。川芎は血行を促進して瘀血を除き、頭痛や月経不順を改善する生薬です。当帰や芍薬との併用により女性の血の巡りを総合的に整えます。山梔子は心や肝の熱を冷まし、精神的な高ぶりや不眠、顔面紅潮などの症状を和らげる生薬です。
消化器官が弱い
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
構成生薬:黄耆(おうぎ)・人参(にんじん)・甘草(かんぞう)・当帰(とうき)・白朮(びゃくじゅつ)・升麻(しょうま)・柴胡(さいこ)・陳皮(ちんぴ)・大棗(たいそう)・生姜(しょうきょう)
口の粘膜は、漢方では消化器官の一部として扱うので、消化器官が弱く体力がない場合は、消化器官を立て直し体力を補うことで口内炎に対処します。補中益気湯は、慢性的な疲労・食欲不振・倦怠感・元気が出ない・胃下垂や脱肛などの内臓下垂・風邪をひきやすい体質の改善に用いられる漢方薬です。黄耆は強力な補気作用(体力を補う作用)を持ち、体表の防衛力を高めて風邪を予防するとともに、体の中心から気を補って疲労を回復させます。人参もまた優れた補気薬で、消化吸収機能を高めて元気を養い、体力を根本から支える生薬です。甘草は他の薬の調和をとりながら脾胃を助け、また鎮痛・緩和作用によって胃腸の緊張を和らげます。当帰は補血薬として血の不足を補い、血行を良くして顔色や肌の状態を改善する生薬です。白朮は脾を強めて水分代謝を助け、胃腸機能を高めて消化不良やむくみを改善します。升麻は持ち上げる作用に優れ、体内の下がった気を引き上げることで胃下垂や脱肛、子宮下垂を改善する生薬です。柴胡はストレス症状を和らげて気の巡りをよくし、情緒不安や胸のつかえを解消して気分の落ち込みを改善しつつ、升麻とともに昇提作用を補います。陳皮は胃腸の動きを良くして気を巡らせ、消化を助けて食欲を増進させます。大棗は補気と健脾の作用により胃腸を保護し、精神を安定させる働きがあります。生姜は胃を温めて消化を促進し、冷えからくる胃腸の不調を改善します。 消化器官が弱すぎる場合は六君子湯(りっくんしとう)・四君子湯(しくんしとう)、血が不足している場合は人参養栄湯(にんじんようえいとう)を使う場合があります。
口内炎には大阪の加美漢方薬局にご相談を
一般的に、口内炎はビタミンや抗炎症剤で対処されます。けれど、漢方薬は口内炎になりやすい体質の改善も抗炎症にも役立ちます。
多くの漢方薬をご紹介しましたが、お一人お一人の体質、症状によってお合わせする漢方薬は違ってきます。大阪・加美漢方薬局では体質、症状を詳しくお聞きし、一番適した漢方薬をお合わせ致します。 何でもお気軽にご相談下さいませ。
全国の皆様よりお電話でご相談承ります。お気軽にご相談ください。
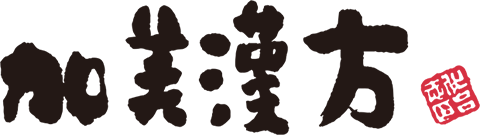
Address. 大阪府大阪市平野区加美東3-17-16
Phone. 06-6793-0609
Open. 10:00-18:00
Holiday. 木曜・日曜・祝日
kamikanpou